 ちょこママ
ちょこママ「受験が不安で勉強どころではない!」そんな受験生やその親御さんのお役に立ちたくて書きました



ちょこママと子どもの体験談も含まれているから、リアルで実践しやすいと思うよ!
【この記事を読むとわかること】
・受験の不安の原因
・受験の不安の対策
・受験に前向きなれるコツ
体験からわかった答え「受験は最後までわからない!」
このブログを見つけた人は、受験が不安になって苦しくなった受験生やその親御さんではないでしょうか。
特に夏休み明けの模試でよい結果がでなかったりすると、夏休みを上手く活用できなかったと焦りだして、不安が増幅しますよね。
夏休みが過ぎると秋、冬と日も短くなって、気持ちも塞ぎ込みがちになります。
このブログの運営者のちょこママも高校3年の大学受験は不安で焦って空回りをしていました。
焦りとストレスからか原因不明の風邪?で、高3の5〜6月は入院と自宅療養を余儀なくされました。
血尿がでて、病院に行ったら即入院でした。
夏休みからは体調も戻ったのですが、想定外の体調不良で焦りまくって、自分のペースをつかめず、
結果、志望校に不合格・・・
でも、その後、超氷河期の時代に公務員試験を独学で1発合格。
実は公務員試験も試験1月前の大事なときに、熱はないけど咳が止まらない風邪にかかり、また直前にペースが乱される事態になりましたが、合格できました。
娘2人は中学受験で模試E判定から逆転合格しました。



↓E判定からの合格のためにやったことはこの記事です↓
E判定からの合格の秘密
私と娘の合格は偶然ではありません。
私の大学受験の苦い経験から不安との向き合い方を学び、合格を勝ち取ったものです。
受験を経験した人はわかると思いますが、合格確実と思われた人が落ちて、無理を言われた人が合格することがあります。
実はそんなに差はないし、受験に絶対はないのです。
このブログを読んで、今は辛いかもしれませんが、受験を最後まで諦めずやり通そうと前向きな気持ちになってもらえると嬉しいです。
一生懸命やった事は、結果はどうであれ、これからの長い人生で力となります。
合格したら、「やればできる!」と自己肯定感爆上がり!!
不合格でも、冷静に分析して、ちょこママのように次の試験で挽回する。そして将来の子どもの教育に活かすことができます。
失うものは何もないのです。
そう思うと、少し気が楽になります。
不安は誰でもあるし、受験じゃなくても、人生に不安はつきものです。
不安は悪いだけではありません。
適度な不安は行動するための原動力となります。
上手く不安と付き合う方法を学んで、人生をよりよくしていきましょう!
まずは、
深呼吸を3回
少し落ち着いたかな?
では、はじめていきましょう。
受験の不安は誰にでも「あるある」


受験は初めての「人生の選択」であり、子どもにとっても親にとっても未知の連続。
だからこそ受験で不安になるのは当然なのです。
受験を真剣に考えているから不安になるし、むしろ不安になるのは自然なことです。
うちの子たちは、県立中学受験の時、最初の模試でE判定が出た時は、これから頑張ればいいやくらいに思っていました。
しかし、入試日が迫ってくるにしたがって、成績が上がらなかった時は本人も親の私も焦りました。
「こんなんで本当に合格できるの?」と、不安と焦りで眠れない日もありました。
でも大丈夫。
不安は誰にでもあるからこそ、乗り越える方法もちゃんとあります。
この経験から学んだことを、今日この記事でお伝えします。
受験で不安が生まれる3つの原因
ここで、なぜ不安になっているかを少し深堀りしていきます。
原因がわからないと対応できません。
ひとつひとつ原因と対策を考えていくと、やるべきことが明確になり、不安は味方になってくれます。



その前に、受験のゴールを再確認するよ
【前提】受験のゴールは?合格とは?
受験のゴールは志望校の入試の合格点をとること
↓
そのためにやる事、できる事は
過去問を合格ラインまで解けるようになること
極端に言うと、その間の模試の点数なんて関係ないのです。
更に言うと、入試の日までに、自分の学力をピークにして合格ラインにもっていけるようにすること
だから、模試で一喜一憂する必要はありません。
志望校によっては、内申点を重視するなら、その対策をする必要がありますが、そうでなければ、過去問をいかに解けるようになるか考えなければなりません。
不安の原因①:志望校合格ラインまでの実力不足・スランプ
受験の不安は、勉強しても成績が上がらない時期=スランプが引き金になることが多いです。
スランプとは、一時的に不調になることです。
努力しても結果が出ないと、「自分には向いてないのかも」と思ってしまい、自信を失ってしまうからです。
うちの子も、頑張っても模試の点数が伸びない時期がありました。
模試の結果をみて、「勉強したのに・・・」と涙を流していたのを覚えています。
でも、ちょこママは、これは誰にでもある「停滞期」だと知っていたから、親として落ち着いて支えることができました。
スポーツなど、物事ができるようになる過程では、成長は階段のように少しずつ上がっていく時や、途中で停滞して、ぐっと上がる場合があります。
「停滞期」はプラトーといいます。似た言葉に「スランプ」がありますが、スランプは一時的に能力が発揮できなくなる状態を指し、プラトーは成長が停滞している状態を指す点で異なります。
停滞期はちょうど階段の踊り場のようなものです。
停滞時は、勉強しても上がらないし、自分には才能がないのかなと諦めたくなる辛い時期ですが、そんな時こそ冷静になって、頑張る時です。
停滞の後、少しずつ成長し始めたり、また、ぐっと成績が上がることはよくあることです。
親は当人でないからこそ、少し俯瞰してみることができます。
そして、この停滞期は、やり方を変えるサインなのか、実力を溜めているときなのか見極め、停滞期は誰にでもあることだと伝えてあげましょう。
プラトー(停滞期)やスランプ(一時的な不調)は受験に付きもの。
「あ、今そういう時期なんだな」と理解するだけでも、不安はかなり和らぎます。
不安の原因②:周囲との比較・プレッシャー
受験と不安は、友達や親せきとの比較、そして期待によって生まれることもあります。
「○○くんは偏差値60あるらしいよ」「△△ちゃんはもう志望校決めたって」……
そんな情報がプレッシャーになってしまうのです。
親の私も、正直「周りの子はもっと進んでるのに」と思ってしまったことがあります。
でも、口に出すと子どもはさらに不安になります。
だから、グッとこらえて「あなたはあなたのペースで大丈夫」と伝えるようにしていました。
子どもによって得意不得意があるので、進み方が違うのは当然なので人と比べる必要はないのです。
他人との比較は、子どもだけでなく親も不安を呼びます。だからこそ、比較を手放す勇気が必要です。
不安の原因③:入試制度の変化・親の知らなさ
受験と不安は、親世代と違う制度や情報の多さによっても生まれます。
特に大学入試は近年どんどん変わっており、
「共通テストって何?」「総合型選抜ってどうやるの?」
と親も混乱しがちです。
私は最初、「総合型(AO入試)」なんて全く知識がなくて、ネットでも調べました。
情報が分からないままでは、親も不安になり、子どもに正しいサポートができません。
親が正しい情報を知ることで、子どもを安心させてあげることができます。
知らないままでいるのは、親子ともに損です。
少し古いのですが、2020年の文部科学省の調査では、子どもの半数以上が親からのアドバイスを求めており、親は入試制度がわからないため、アドバイスが難しいと回答しています。
専門的なことは学校や塾に敵わないとしても、子どもがもとめているある程度調べて、親子で一緒に考える姿勢をもつことは、子どもの不安を軽減できる有効な方法となります。
↓12ページ「保護者からのアドバイス/アドバイスしてほしい内容」参照
受験の不安への7つの対策


これから、受験の不安を減らす具体的な7つの対策を紹介します。
(1)受験の不安をノートに書き出す
受験と不安に押しつぶされそうなときは、まずノートに書き出すだけでラクになります。
頭の中だけでグルグル考えると、不安が増してしまうからです。
うちの娘は基本的に今日勉強した事だけを寝る前に書いて、気が向いたら、不安に思っていることや解決策を書いていました。
入試が近づいて、不安が大きくなっていく時期にこのノートに書く習慣で、不安に溺れることなく冷静を保てたと後で話してました。
※うちの長女は、中高一貫校に通ってましたが、その後、どうしても高専に行きたいと、当時偏差値が足りなくて、最初は学校や塾の先生にもそんな危険なことするよりそのまま今の高校に進んだ方がよいと反対されましたが、意思を貫き、みごと高専に合格しました。
ちなみに、もし高専を受けて落ちた場合でも、もとの高校には進学できないという決まりがあり、高専に行けなかったら、高校を受け直さないといけない状況でした。
書くだけで気持ちが整理され、不安が現実的な課題に変わります。
(2)具体的な学習計画で不安を減らす
「いつまでに」「何を」「どれだけやるか」を決めることで、受験と不安に立ち向かいやすくなります。
受験のゴールは、雑に言うと「志望校の過去問が合格ラインまで解けるようになること」です。
関係ないことは全て捨てて、今の自分の学力(スタート時点)から合格ゴールにどうしたら到着できるかだけ考えてみましょう。
自分の今の学力を考えず、周りと同じことをやったり、焦って行き当たりばったりやると、成果が見えずにますます焦るという悪循環に陥ってしまうからです。
自分でよくわからない場合は、今の自分の学力と志望校の過去問を見せて、学校や塾の先生に相談してみてもいいかもしれません。
そして、「何月までにこのテキストを2回繰り返す」など具体的な計画と立てていくと、やることが明確になって、行動することで不安に溺れることが少なくなります。
先が見えるようになると、不安は少しずつ和らいでいきます。
もし、学校の先生が
(3)親子対話・相談相手を持つ
受験と不安を乗り越えるには、「気軽に話せる人」が必要です。
一人で抱えると不安は大きくなりがちですが、話すことで気持ちは軽くなるからです。
母親の私は、子どもが受験の話をした時は、聞き役に徹するよう気をつけました。
それは、私が大学受験の時、親に話した時、正論ばかり言われて嫌になった経験があるからです。
当時の高校生の私は「そんな事はわかっている。できないから困っているのに親はわかってない。親は大学受験をしたことないからわからないんだ。あーイライラする!!」って、時々思っていました。
親が心配してくれているのはわかっています。でもその時はもう、余裕がないからそんなことは考えられないのです。
大人になって、高校生の私は「ただ話を聞いてほしかっただけなんだ」と気づきました。
だから、自分の子どもたちには、受験に関して話を聞く時、つい正論をいう場合もありましたが、表情をみてイラついてきているなと思ったらすぐにこちらが折れるようにしました。
親と話して勉強のやる気がでれば、それが正解。逆にやる気をそぐようなら不正解だから、次回は言い方に気をつけようと考えて接していました。
子どもが話せる“空気”を作ることが、親にできる一番のサポートかもしれません。
(4)本番対策&緊張緩和法
受験と不安に備えるには、「本番の練習」と「緊張対策」が欠かせません。
緊張しすぎて頭が真っ白になるのを防ぐためです。
我が家では模試の前に、試験と同じ時間に起き、同じ朝食をとり、机に向かうリハーサルをしていました。
「やったことがある」という経験が、本番での落ち着きにつながったようです。
学校説明会なども志望校に行く機会があれば、なるべく参加するようにしました。
本番の入試で初めていくのは環境の変化が大きすぎて緊張が大きくなると考えてたからです。
前日の夕食もカツなど縁起をかつぐことなく、普段食べているものを食べていました。
“慣れ”は最大の安心。
家庭でも試験本番をイメージした練習をしておくのがおすすめです。
(5)親の関わり方と“安心できる居場所”
受験と不安に向き合う子どもにとって、親の対応次第で安心感が大きく変わります。
プレッシャーをかけるより、「あなたなら大丈夫」と信じてあげる姿勢のほうが、子どもの心を支えます。
私はあえて「頑張れ」と言わず、「今日もよくやったね」「なんとかなるさ」と声をかけていました。
疲れている日はお風呂を沸かしておくだけでも、「わかってくれてる」と感じるようでした。
先程の(3)の相談相手について述べた通り、
正論ではなく、親と話して勉強のやる気がでれば正解。
子どもをイライラさせて、かえって勉強の妨げになったら不正解
と判断して、子どもがやる気になる言動を心がけました。
子どもがホッとできる家であること、それが何よりの不安対策になります。
(6)呼吸を整える「1分瞑想」で心をクールダウン
受験と不安でいっぱいになったとき、瞑想が心を落ち着けてくれます。
深い呼吸に集中することで、気持ちが整い、ストレスが減るからです。
すぐにできるのが1分間の呼吸瞑想。
「鼻から4秒吸って、口から6秒吐く」を数回繰り返すだけで、表情がやわらぎます。
子どもが緊張している様子のとき、一緒にやってみるのもおすすめです。
道具も時間もいらない“お守りのような習慣”として、1分瞑想はかなり使えます。
もう少し瞑想してみたい方はこちらの動画がおすすめです。
この動画で、実際に瞑想でき、瞑想の効果も端的に説明してくださるので、ちょこママはこの動画を頻繁に見て瞑想しています。
おすすめ瞑想の動画がコチラ↓
上のyoutube動画がエラーの場合はこちらをクリック!解説付き5分瞑想
紹介した動画は23分ありますが、一度見てもらえると、瞑想が不安軽減にいかに良いかがわかります。



この動画は瞑想が日常生活で役立つことをわかりやすく教えてくれます
(7)不安をやわらげる「脳にやさしいおやつ」
受験と不安を抱えるときは、ちょっとした食べ物でも気持ちが変わります。
食べ物に含まれる栄養素が、脳や気持ちを整えるホルモンの原料になるからです。
うちの子は勉強の合間によくラムネを食べていました。
脳のエネルギーになるブドウ糖が含まれているからです。
食べやすいし持ち運びしやすいし、カバンに入れて置くだけでも安心感がありました。
その他、普通のミルクチョコレートもいいですが、できればハイカカオのチョコレートも有効です。
また、不安な時は、精神を安定させる効果があるトリプトファンが多く含まれている食べ物も有効です。
「バナナ、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、ナッツ類、大豆製品があります。どれもコンビニで手軽に買えるので、気分に合わせて取り入れてみましょう。
手軽なおやつが、実は心のケアにもつながる。気分転換に取り入れてみてください。
終わりに:小さな一歩が自己肯定感につながる
受験と不安は、完璧じゃなくても“一歩踏み出すこと”で軽くなります。
少しの行動が「自分でもできた」という自信につながるからです。
今日できたのは英単語10個でも、ノート1ページでも、それが続けば確かな力になります。
毎晩ノートにやったことリストを書いて、行動できた自分を褒めて眠りにつきましょう。
今日からでも遅くありません。あなたとお子さんが、一緒に歩んでいけますように。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が少しでもあなたの不安を和らげるお手伝いができれば幸いです。

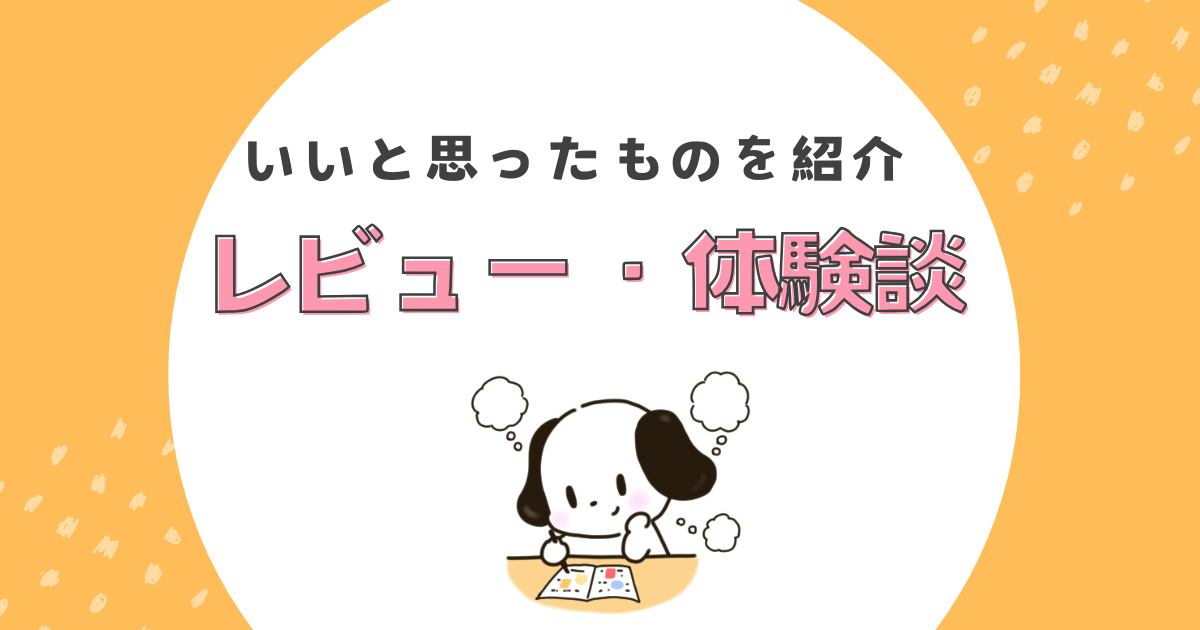
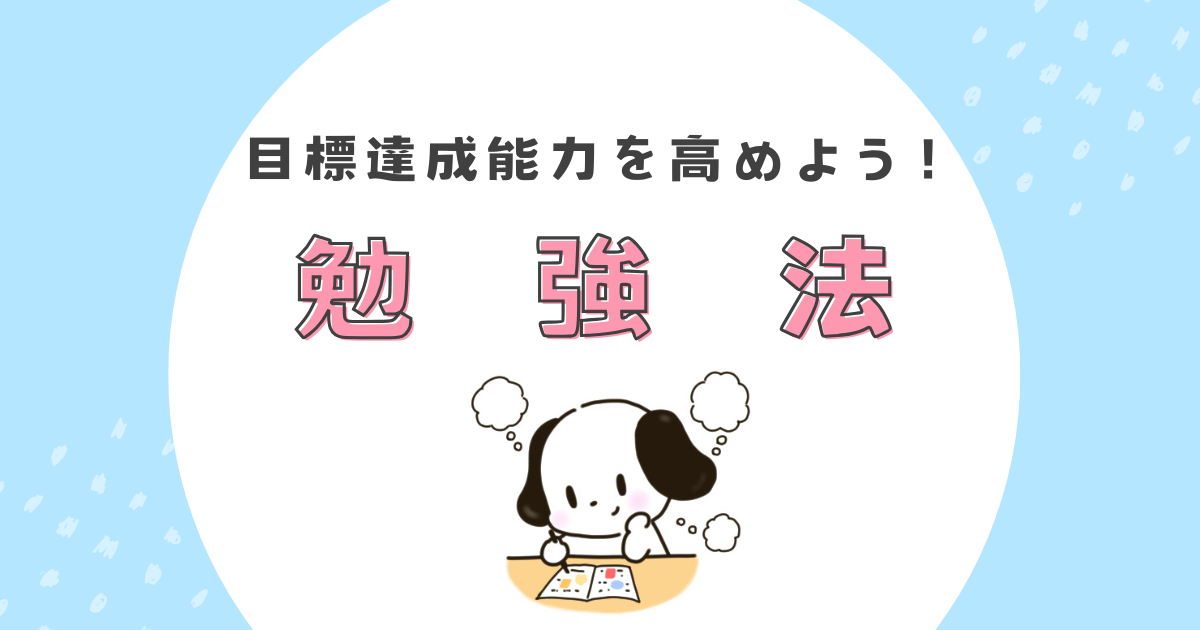

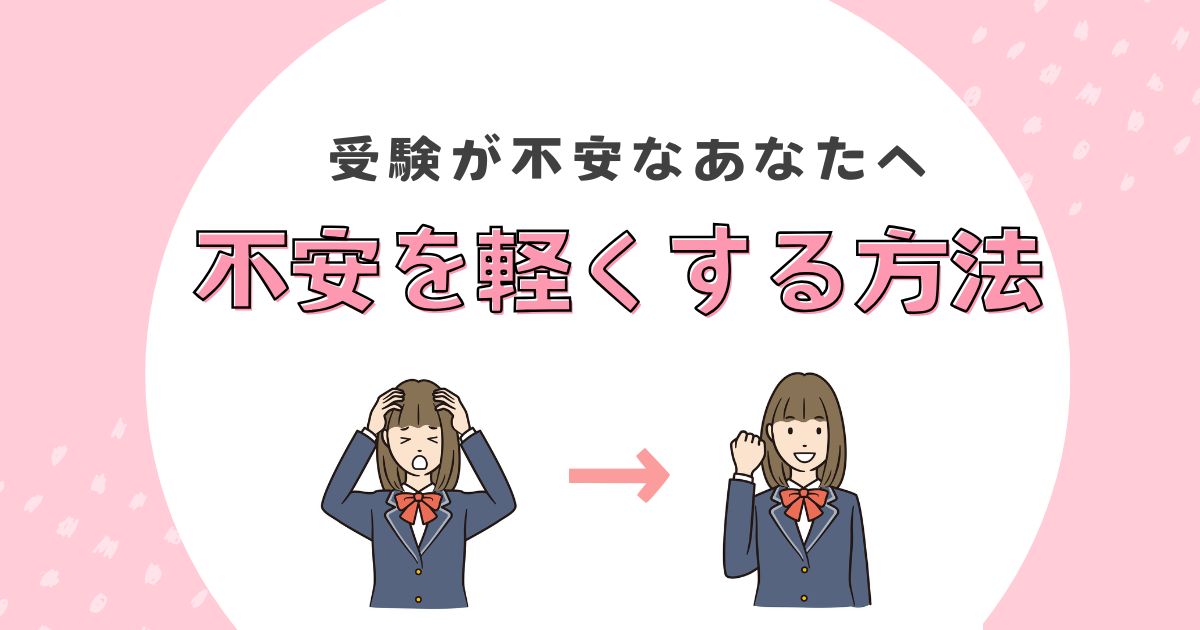


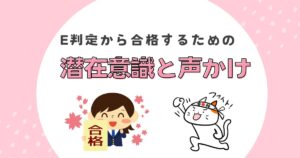
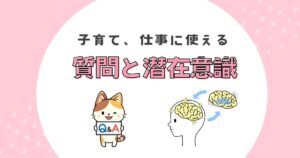


コメント(ご記入いただいたメールアドレスがブログ上に公開されることはありませんので、ご安心ください。)